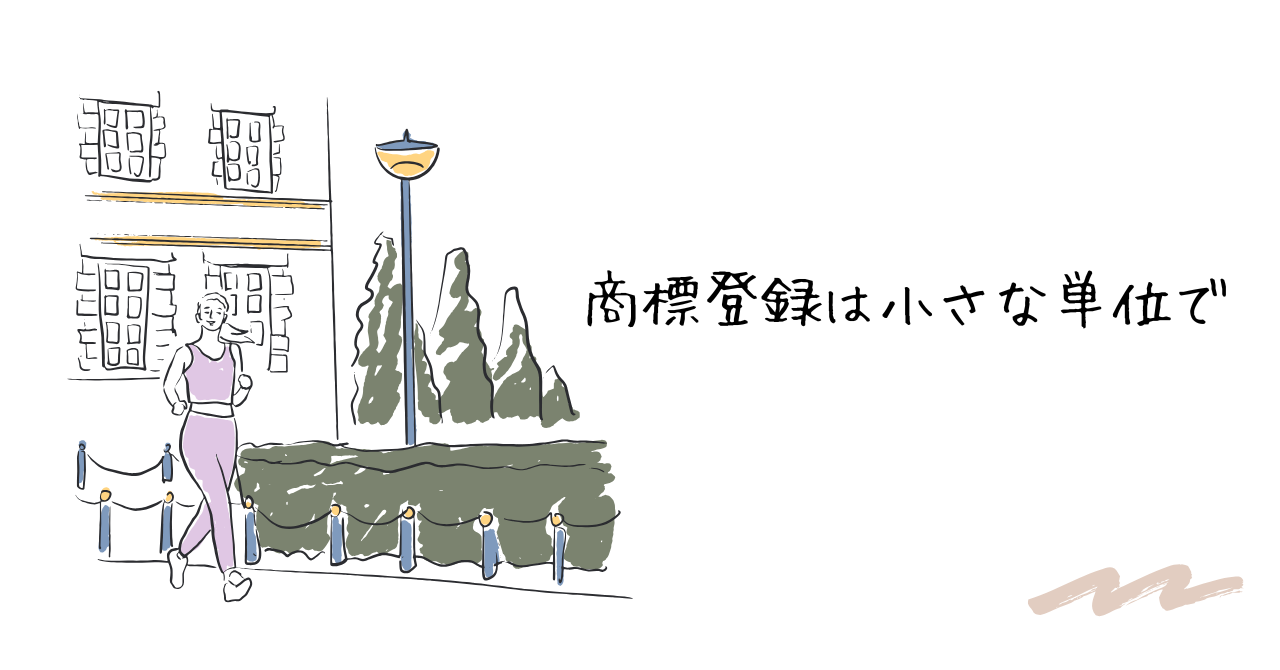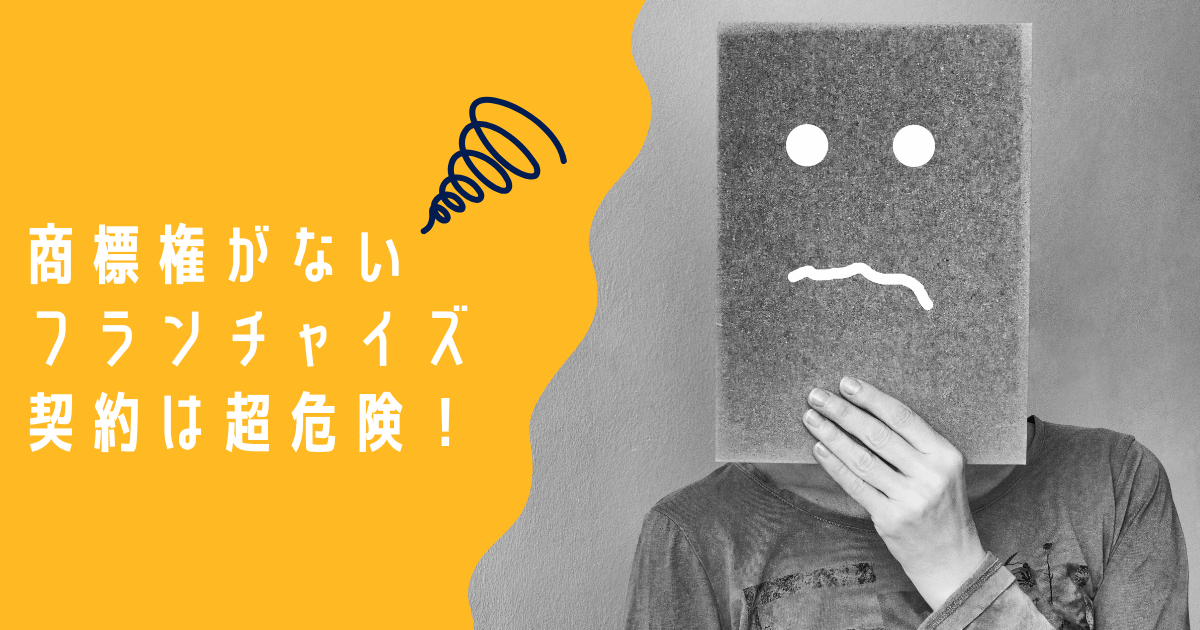あなたが考えた商品名やサービス名を商標登録しようとしたとき、「識別力がない」という理由で拒絶されたら、どうすればいいのでしょうか?
「拒絶=使ったらダメ?」と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。
今回はそういったケースで「使い続けてよいのか」「審査でどこまで対応すべきか」について、できるだけわかりやすく解説します。
「識別力がない」とは?
商標とは、その商品やサービスがどこの会社のものかを示す目印(名前)です。
その名前が造語であれば、その名前が付けられた商品・サービスがどこの会社のものか区別できるように、その名前について(ざっくり言うと)一業種一社しか使えないようにすべきです。
一方、商品やサービスの中身をそのまま表すような言葉は、誰でも使えないといけないから特定の会社に独占させるべきではないという考え方があります。
このように、「みんなが使うべき言葉だから登録できません」と判断された場合、その商標は「識別力がない」として拒絶されます。
識別力なしの拒絶査定=「みんなが使える」
つまり、識別力なしの拒絶査定は、独占はできないけど使うことはできる、ということになります。
ということは、「登録できなくても自分が使えればいいや」と思えば、拒絶理由通知時に労力やお金をかけて意見書を特許庁に提出する必要が無いようにも思えます。
しかし将来的なリスクはゼロじゃない
ここで注意したいのは、後から別の誰かが同じ商標で出願し、登録に成功してしまう可能性がゼロではないということです。
例えば、先発の出願人(あなた)が出願し識別力なしで拒絶査定になった後で、後発の出願者が同じ商標を出願すると、その後発の出願人にも当然識別力なしの拒絶理由が通知されます。
しかし、後発の出願人がその拒絶理由通知に対して意見書を提出して反論し、それでも拒絶査定となっても諦めずにさらに拒絶査定不服審判を請求して登録が認められる可能性もあります。
もちろんこのようなパターンは確率としては低いですが、そうなったときには自社が商標の使用を後発的に制限されるということは頭に入れておく必要があります。
こうしたリスクが現実となった事件もあります。
音楽マンション事件
たとえば、「音楽マンション事件」と呼ばれる事例があります。
商標「音楽マンション」を出願した会社(A社)は「識別力がない」として拒絶され、それに対し審判請求をせずに拒絶を確定させました。
その後、別の会社(B社)が改めて「音楽マンション」を出願し、拒絶理由通知に対して意見書を提出し、その主張が認められ登録に成功。
識別力が無いと判断され安心して使用していたA社は、その後でB社の商標権侵害になりました
当然、A社は文句を言いましたが、裁判所は「A社は拒絶査定不服審判をやる機会はあったのに、その努力をしてないじゃん(意訳)」としてA社の主張を認めませんでした。
拒絶理由通知後、どこまで対応すべきか?
音楽マンション事件を踏まえ、どこまで対応しておけば識別力なしとして拒絶になった商標を安心して使用できるでしょうか?
まず、それを検討する前に、その検討に必要な、先行商標調査でわかることを説明します。
先行商標調査でわかること
出願前には通常先行商標調査を行います。
その先行商標調査によってわかることは、今から出願しようとしている商標が既に出願や登録がなされているかだけに限りません。
それらの出願経過もわかります。
すなわち、
・今から出願しようとしている商標が他人によって出願されたかどうか
・拒絶理由が通知されたか、一発で登録されたか
・拒絶理由が通知されて意見書を提出したか
・拒絶理由通知書や意見書の内容
・拒絶査定の後に拒絶査定不服審判が請求されたか
・その出願に代理人として弁理士が付いているか
などが、先行商標調査ではわかります。
拒絶理由通知後のパターン
拒絶理由通知を受けた後に結果的に拒絶が確定するパターンには、現実的に以下の4つのパターンがあります。
① 意見書を出さずに拒絶査定
→反論を一切行っていないので、同じ商標を出願しようとする他人が「自分なら意見書を書いたら登録できる」と思う可能性があり、他人が同じ商標を出願することに対する抑止力は低い
② 意見書を提出したが拒絶査定
→「意見書で反論しても通らなかった」という履歴が残り、他人が同じ商標を出願することへの抑止力がある程度期待できる
③ 拒絶査定不服審判を請求したが拒絶審決
→審査官と審判官の両方に否定された事実が残り、他人の出願意欲がかなり下がる
④ 審決取消訴訟まで提起したが棄却(拒絶審決)
→司法判断まで出た商標と見なされ、さらに強い抑止力が期待される
①のように、意見書すら出さずに終わってしまうと、出願者が本気で登録を目指していなかったと見なされ、後発の出願予定者が「自分なら通せるかも」と思ってチャレンジするリスクが残ります。
一方で②のように意見書を出した上で拒絶されたという履歴がJ-PlatPatに残っていれば、「誰かが一度きちんと反論したが、それでも登録されなかった」という記録として、一定の抑止力を持ちます。
特に、その意見書を弁理士が書いていればより抑止力としての効果が高いでしょう。
さらに③や④まで進んでいれば、他の誰が出願しても通らないと認識されやすくなり、安全に使える可能性が高まります。
この論文によると、2015年からの5年間で、識別力なしの拒絶理由通知に対し意見書を提出せずに拒絶査定になり、同じ商標を後から他人が出願して登録査定になった事例が19件あるようです。
意外と多くないですか?
結論:使い続けるなら、最低でも意見書は提出しよう
「識別力がない」商標は、独占できないだけでみんなが使えると判断されたということです。
それでも、後から誰かが登録に成功する可能性はゼロではありません。
そのリスクを下げるためには、反論した履歴をJ-PlatPatに残すことが重要です。
最低でも意見書を提出して拒絶査定となることが重要で、音楽マンション事件を踏まえるとできれば拒絶査定不服審判まで行い、後発出願への抑止力を強化することが望ましいといえます。
「出願して自分が使えることを確認したいだけ」という場合であっても、少なくとも意見書提出までは予定に入れておきましょう。
(文責:弁理士 松本文彦)
Web会議にて全国対応可能