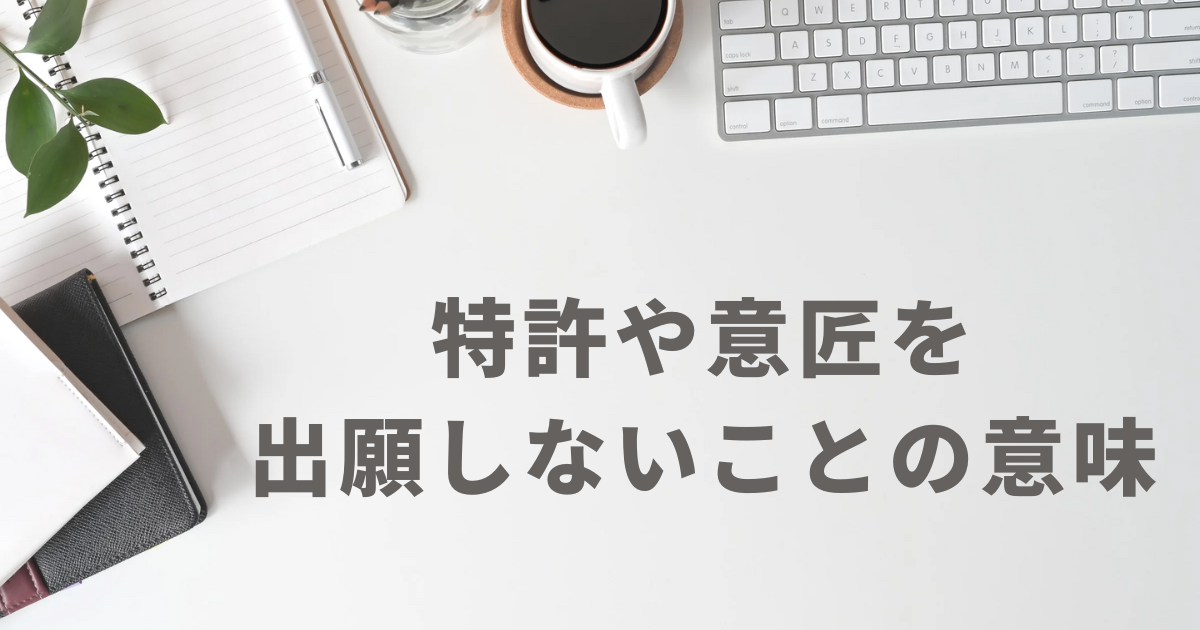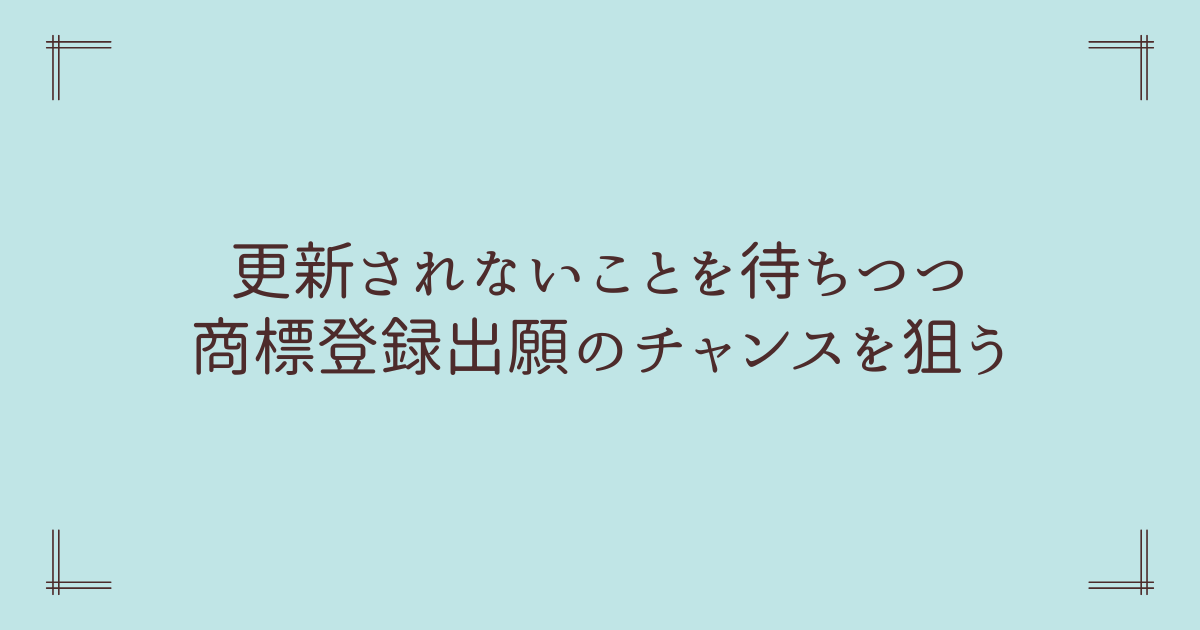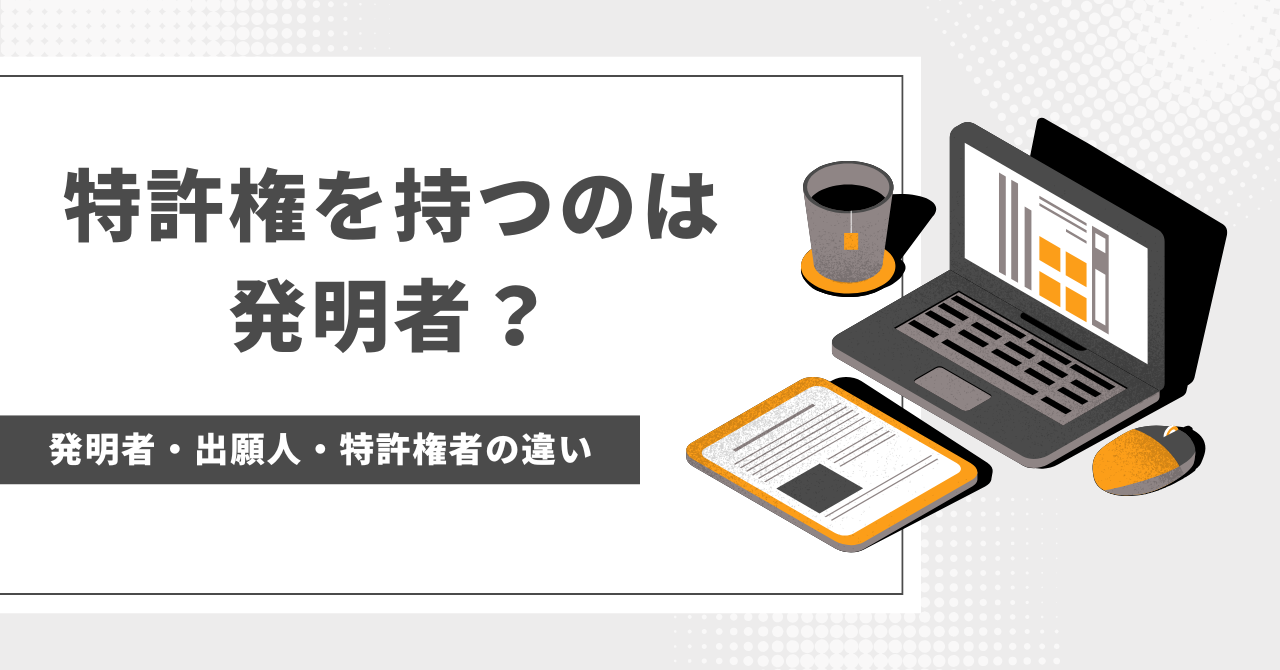新しい製品やサービスを目にしたとき、「これ、真似してもいいの?」と疑問に思ったことはありませんか?
実は、他人のアイデアや製品を“真似する”ことは原則として許されている行為なのです。
もちろん例外はあります。特許権や意匠権などで保護されたものを真似してしまうと、権利侵害にあたります。
以下では、特許や意匠の出願をせずに製品・サービスをリリースするということが、どのような意味をもつのかを分かりやすく解説していきます。
「真似すること」は原則OK
まず大前提として、アイデアや製品を真似すること自体は法律上の問題はなく、原則として許される行為です。
「学ぶ」=「真似ぶ」だとも言われるように、人が何かを学ぶときにはまず真似をすることから始まります。
しかし、この原則があてはまらない“例外”があります。
それが、すでに特許権や意匠権などで保護されている場合です。特許を取られた技術や意匠権を取られた形状を勝手に真似して使うと、権利侵害になってしまいます。
出願しないのは「共有財産にする」ということ
もし、ある企業が特許や意匠などの出願をしないまま新しい製品やサービスを世の中に出したとします。
その場合、その企業は「自分たちだけが独占できるはずの技術やデザインを保護しない」と選択したことになります。
つまり、誰でも同じ技術やデザインを使って製品化したり、サービス提供したりして構わない状態を自ら作っているのです。
ここで、「ただ特許を取っていないだけ」「知らなかった」「そんなつもりはなかった」というのは通用しません。
保護したいのであれば、そのための手続き(特許出願や意匠登録出願)を行わないといけない、というルールなのです(営業秘密等の例外あり)。
真似するなんてモラルがない?
SNS(特にX/旧Twitter)などを見ていると、「真似をするなんてモラルが無い!」という投稿や、「日本人としてどうなんだ」など感情的な言葉を見かけることがあります。
しかし、特許法等に「特許権を取ったら一定期間独占できるよ」と書かれており、その反対解釈をすると「特許や意匠などの権利がなければ、基本的に他社が真似してもOK」がルールです。
法治国家においてルールに基づいて行動したにもかかわらず「モラルがない」と言うのは、それを言うこと自体がひどいことだと思いませんか?
競合他社の出願状況のウォッチング
弊所の顧問先様の中には、競合他社が新サービス・新機能をリリースしたらそれについて特許出願がされていないか、そのような特許出願が後々公開されないかウォッチングするよう依頼をいただく会社様もおられます。
そのようなことにコストを掛ける理由は、競合他社がどのような特許や意匠を出願し、どの範囲まで権利を取ろうとしているか・取ったかを確認し、真似をしたらいけない範囲を把握するためです。
逆に言うと、真似をしてもいい範囲の把握にもなります。
まとめ
出願しないで公開するということは、それを人類共通の財産として誰でも使えるようにするということにほかならないので、営業秘密のようにノウハウ管理すべき例外を除き、「他社に真似されたくない大事な技術・デザイン」であれば特許や意匠を出願し権利化することを検討しなければいけません。
お気軽に「これ、真似されたくないんだけど特許などで保護できる?」とご相談ください。
・特許出願
・意匠登録出願
・ノウハウ管理
・そもそも保護する術は無い
など事案に応じて適切にアドバイスいたします。