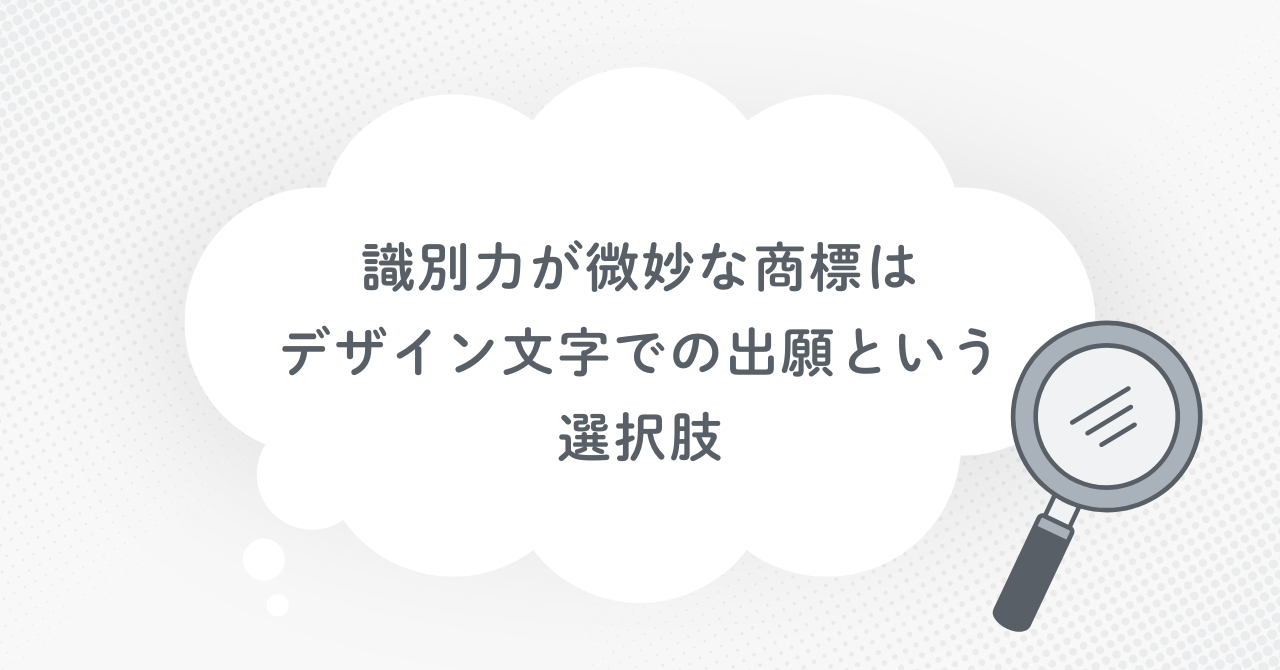多くの中小企業経営者にとって「知財=大企業のもの」「特許はうちには必要ない」というイメージがあるかもしれません。
しかし実際には、たった1件の特許権や意匠権があるだけで、営業活動や販売契約等に大きなインパクトを与えることがあります。
今回は、私が実際にサポートさせていただいた中小企業のお客様の中から、知財を上手に活用して 売上アップや契約獲得につなげた成功事例を3つ ご紹介します。
受注数が1.5倍に
弊所のクライアントである中小企業A社は販売会社B社と、ある新商品の共同企画・開発プロジェクトを進めていました。
A社が商品を製造してB社にOEM供給し、B社が一般販売するという協力体制です。
B社としては「たくさん売って儲けたいけど不良在庫は抱えたくない」というのが本音ですよね。
不良在庫が最も多くなるパターンが、他社の特許権侵害や意匠権侵害になり商品を1つも販売できなくなってしまうことです。
ここで、競合他社の登録意匠に似ていると言われかねない製品をA社とB社が製造・販売しようとしたため、その競合他社から警告が来るおそれがありました。
そこでA社はその商品に関して弊所が代理をして意匠登録出願を行い、約半年後に無事に意匠登録できました。
つまりこれは、A社の登録意匠と競合他社の登録意匠が非類似である、と特許庁が認めたということになります。
そのことをA社がB社へ報告すると、B社の担当者が「安心して販売できる」と喜んで、当初の販売計画を見直し、B社からA社への発注数が当初予定の1.5倍になりました。
もし意匠登録できていないとずっと不安なまま販売し続けてなければいけませんし、その競合他社も「B社にはいつ警告してやろうか」と思うはずです。
権利化できて安心を得られたことは商売上かなり意味があります。
また、その競合他社も警告の前には他社の登録意匠を確認するので、その確認時にA社の登録意匠の存在に気づくはずで、A社の登録意匠を無効にしないと警告しにくい状況になりました。
BtoBでのシステム採用の後押しに
弊所のクライアントである中小企業C社は、あるシステムについて仕様を確定させた段階から「これはいける!!」と確信し、そのシステムを導入してもらおうと大企業D社に提案していました。
もともとC社は「特許出願中」としてD社に売り込むために、このシステムについて特許出願するつもりではありました。
それに加え、「特許権取得済み」としてPRするほうがD社により採用してもらいやすいだろうとC社社長は考え、D社の意思決定の時期に特許権取得を何とか間に合わせるように、弊所が代理をして特許出願と同時に審査請求と早期審査の申請を行いました。
その結果、拒絶理由を通知されることなく出願から1ヶ月弱で特許査定となりました。
たとえ早期審査であっても審査結果が出るまで通常2~3ヶ月かかるものですが、その技術分野におけるそのときの出願数がたまたま少ないタイミングだったようです。
そして、この特許権の存在がD社の購買担当者の安心感につながり、D社でのC社のシステム導入が円滑に進みました。
特許権が随意契約の理由に
弊所のクライアントである中小企業E社はあるシステムを構築し、特許出願を行いました。
そして特許出願からまもなくして審査請求及び早期審査の申請を行い、拒絶理由通知は通知されましたが、それにも対応して無事に特許権を取得することができました。
E社は、F社にこのシステムを導入してもらいたいと考えており、E社の営業提案を受けてF社の購買担当者もE社のこのシステムを気に入って是非とも導入したいと考えていました。
しかし、F社は大きな組織であり公共性の高い事業を行っているため、一定金額を超えるシステム導入などは入札が原則となっており、F社の担当者が独断でE社のシステム導入を決めることはできません。
ここで、E社が取得した特許権が、F社によるシステム導入に決定的な役割を果たしました。
E社の特許権の存在が、入札を行わず随意契約しても構わない根拠となったのです。
つまり、特許権があることで特許権者以外は実施できないためそのような場合には随意契約できるという入札の例外が決められている場合は少なくなく、F社にもこの取り決めがありました。
その結果、無事にE社はF社と大型契約を締結することができました。
但し、これが有効であるのは購買担当者が「是非とも導入したい」と気に入っている場合です。
商品・サービスを購入予定者が気に入ってもないのに特許権だけがあっても売れるものではありません。
今回ご紹介した事例のうち2社は、初めて1件の権利を取得した中小企業で、残りの1社はコツコツと出願を重ねてきた中小企業です。
このように中小企業であっても知財を取得したことで受注増・商談成立・契約獲得といった具体的な営業面の成果を得ています。
もちろん、製品・サービスが顧客から求められていることが最も重要ですので、特許権や意匠権を取っても売上に直結することばかりではありませんが、もし「自社も知財を営業活動に活かしてみたい」と思われたら、ぜひお気軽にご相談ください。
Web会議にて全国対応可能